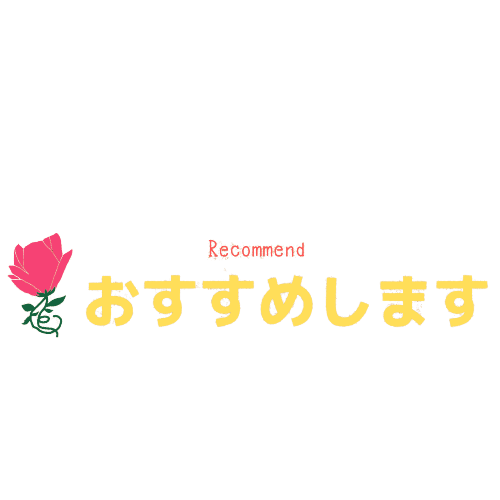忙しく過ごす日々に一杯のお茶で「ホットすること」あると思います。「健康は一杯のお茶から」と言われほどです。お茶のうれしい効用や栄養など紹介します。
お茶とは
お茶はツバキ科の植物で、その葉を摘んで蒸したり、熟したりして加工します。大きく分けては、緑茶は「不発酵茶」、紅茶は「発酵茶」、ウーロン茶などの中国茶は「半発酵茶」に分類されます。それらをお湯で浸出したものを「お茶」と呼び、私たちの身近な飲み物として飲んでいます。

お茶の種類と効用
にはカロテン・ビタミンK・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・ナイアシン・葉酸・パントテン酸が豊富に含まれています。
これらの成分は、浸出した液にはほとんど出てきませんが、その中でカフェイン・カテキン・テアニンなどの水溶性成分は摂取できます。カフェインは脳の覚醒作用・利尿作用があります。カテキンは渋み成分で、高い抗酸化作用・殺菌作用をもち、高血圧予防・歯周病予防の効果があることで知られています。茶葉をそのまま食べても栄養価が上がります。
緑茶(日本茶)
煎茶(せんちゃ)
一般的な標準的な蒸し時間で蒸してから乾燥させた製法でつくられたお茶を「煎茶」と呼びます

深蒸し煎茶
普通の煎茶よりも約2倍長い時間をかけて茶葉を蒸してつくったお茶で、苦味が少なく濃い味わいです。

玉露(ぎょくろ)
新芽が2~3枚開き始めたころ20日間ほど、日光をさえぎり栽培したのが玉露です。旨味が強く、苦味・渋みが少ない。カフェインは多く、集中力を出したい時にお勧めします。

かぶせ茶
茶葉を摘む1週間前から茶園を覆って栽培します。普通煎茶と玉露の中間的なお茶。

玉緑茶(たまりょくちゃ)
葉の形を整える工程を省いた、丸いぐりっとした形状に仕上がったお茶のことです。サッパリした味わいです。

抹茶(まっちゃ)
茶葉を細かく粉にしたものをお湯で溶いて飲むため、お茶の成分をそのまま摂ることができます。お菓子やアイスクリームなどの食品を引き立たせるため、食品素材として広く普及しています。

玄米茶(げんまいちゃ)
水に浸して蒸した米を炒り、これに番茶や煎茶などをほぼ同量の割合で加えたお茶が「玄米茶」です。炒り米の香ばしさと、番茶や煎茶のさっぱりとした味わいが楽しめます。

ほうじ茶
煎茶、番茶、茎茶などをキツネ色になるまで強火で炒って(ほうじて)、香ばしさを引き出したお茶のことです。高温でいることにより、カフェインと少めです。

番茶(ばんちゃ)
摘採期、品質、地域などで日本茶の主流から外れた番外のお茶を指しています。

「伊藤園」ホームページより参照
紅茶(こうちゃ)
銘柄名となっている産地の気候や風土によって、品質や香りが異なり、さまざまな個性を持っています。カフェインはと高めです。

ウーロン茶
中国茶の代表として有名です。製造方法の違いにより、カテキン類は減少しますがポリフェノール類の一種であるテアフラビン類などに変化し、抗酸化・抗菌・脂肪吸収抑制などの働きがあります。油を多く使う料理の際には、ウーロン茶を一緒に飲むと良いとされるのは、このポリフェノール類の効果なのです。

「あすけん」より
お茶は中国では漢の時代から解毒用として珍重され、後に飲用にと発展し、生活必需品となって人々の生活に浸透するようになりました。

今ではペットボトルで気軽に広く親しまれています。日本茶にもたくさんの良い効能があるので、普段コーヒーや紅茶を好んでいる方も、選んでみてはいかがですか?